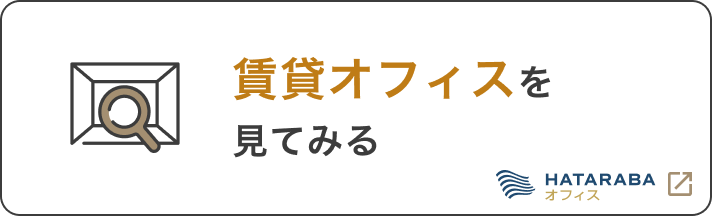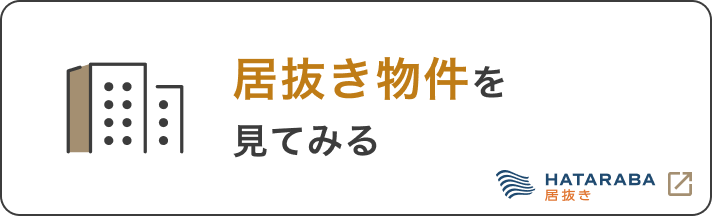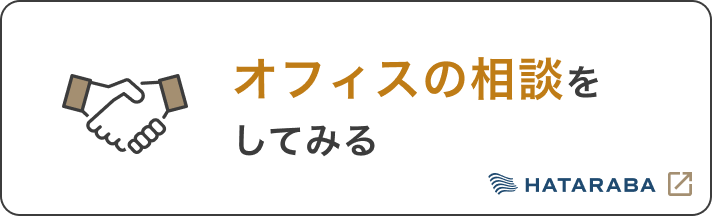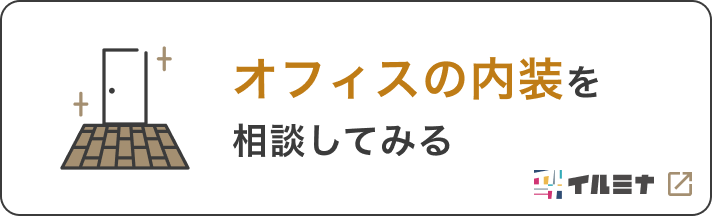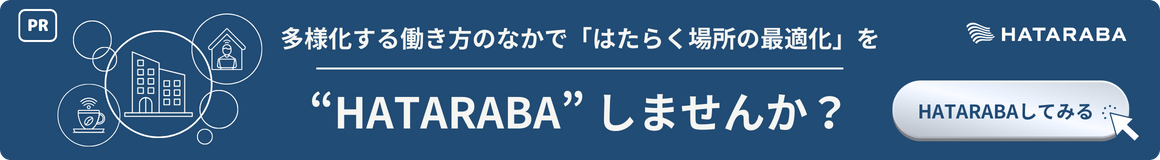-
- ファシリティナレッジ
-
福利厚生の拡充でオフィスが変わる!成功の秘訣と運用ポイントを解説
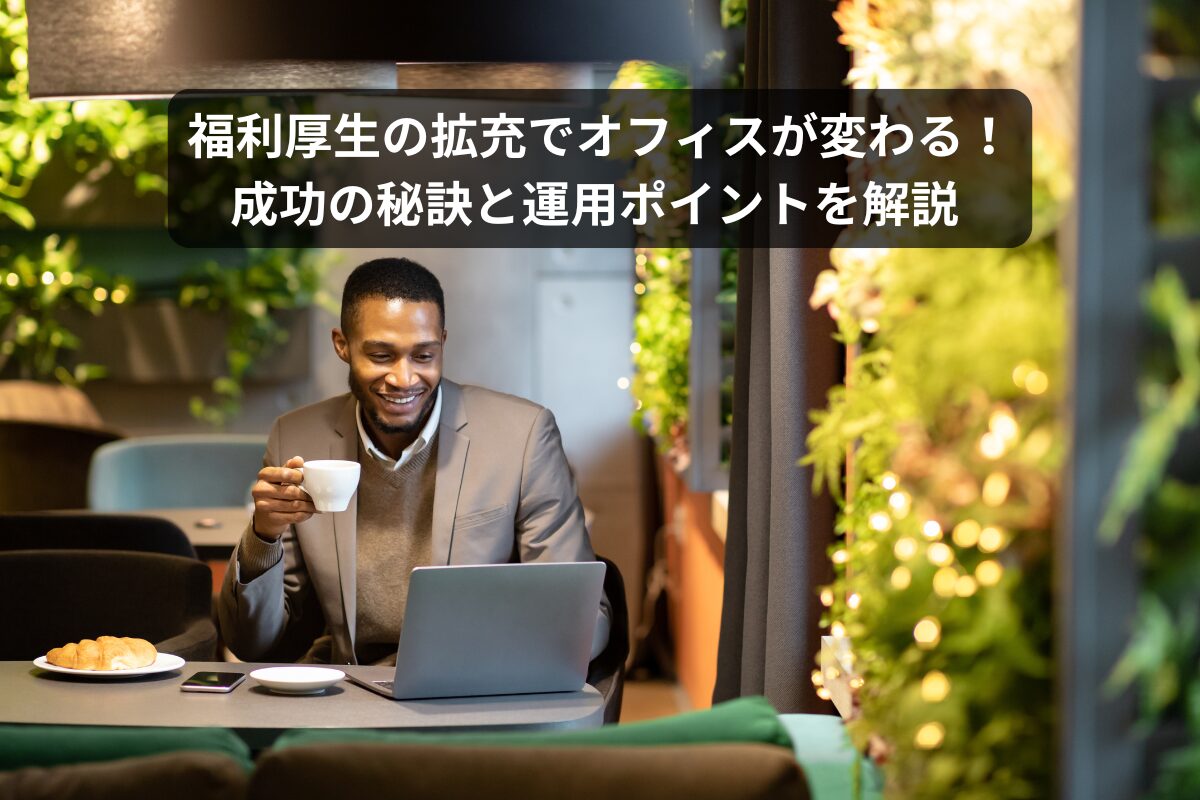
近年、多くの企業が働きやすい環境づくりに力を入れている中、注目されている取り組みの一つが「福利厚生の拡充」です。一方で、社内制度や設備のアップデートを担当している方の中には、具体的な施策がイメージできないという方も少なくないはず。本記事では、従業員からのニーズの高い福利厚生の種類や、オフィスへのスムーズな導入・定着を成功させるためのポイントを解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
オフィスの福利厚生とは?

「福利厚生」とは、企業が従業員に対して提供する様々なサービスや制度の総称です。自社で働く従業員の仕事に対するモチベーション向上をはじめ、本人やその家族の生活の品質向上を目的として設けられており、給与や賞与以外の報酬、各種手当や休暇など、そのカテゴリーは多岐にわたります。
ここではまず、福利厚生の種類と拡充するメリットについて解説していきます。
福利厚生の種類
福利厚生の種類は、「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類に分けられます。「法定福利厚生」は、その名の通り、法律によって企業が設けることを義務付けられている福利厚生です。企業規模や業種にかかわらず全ての企業が、細かく定められた適用条件を遵守し、実施することを義務付けられています。実施にかかる費用は企業負担となりますが、一部費用は非課税の対象となっています。
対して、「法定外福利厚生」は、企業が任意で設ける福利厚生であり、昨今、多くの企業が力を入れているのも、法定外福利厚生の拡充です。法定外福利厚生は、各企業が自社の業種や規模、従業員のニーズなどに合わせて独自に設けることができるため、企業の理念やビジョンの発信と連動させやすい施策の一つとなっています。
法定福利厚生と法定外福利厚生に該当する主な制度は以下の通りです。
法定福利厚生:健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険・有給休暇など
法定外福利厚生:社員食堂・住宅手当・慶弔見舞金・ストックオプション・社員旅行など
福利厚生を充実させるメリット
福利厚生を充実させることは、企業や従業員に対し様々なメリットを生み出します。労働政策研究・研修機構が実施した調査では、若手世代を中心に、勤務先を選ぶ際に福利厚生を重視していることが報告されており、人材不足に悩む企業にとっても福利厚生は、重要な採用戦略の一つとなっています。
出典:労働政策研究・研修機構「企業における福利厚生施策の実態に関する調査―企業/従業員アンケート調査結果―」
また採用後も、福利厚生が充実したオフィスでの勤務により、従業員の仕事への満足度や企業に対する愛着が高まり、定着率・生産性の向上につながることが期待できます。さらには、従業員のパフォーマンスが高まることで、魅力的なサービス・商品の誕生や企業イメージの向上といった効果が生まれ、採用市場においてさらなる優位性の確立にもつながっていくでしょう。
オフィスで導入したい福利厚生
日々多くの従業員が働くオフィスは、様々な福利厚生の導入・実施に適した空間です。オフィス空間を活用することにより、従業員が福利厚生の制度やサービスの存在を実感しやすくなることから利用促進につながり、効果測定が行いやすいという点が大きなメリットです。ここからは、オフィスに導入したい福利厚生をカテゴリー別に解説していきます。
1.健康促進 / リフレッシュ
フィットネスルームやマッサージルーム、瞑想・昼寝用スペース。オフィス内緑化や健康的な社食サービス、スタンディングワークエリアなど
2.ワークライフバランス
リモートワークやフレックスタイムなどの柔軟な働き方に対応したオフィスレイアウト。社内託児所や子連れ出勤用スペースの設置など
3.キャリア / リスキリング
図書館や自習室、集中ブースの設置。様々な部署・役職の人と交流できるフリースペースやカフェテリアの設置など
上記の他にも、近年はストレス軽減効果があるとして、ペット同伴出勤に対応している企業も目立つようになっています。
いずれの福利厚生においても、導入・運用を成功させる鍵はオフィスデザインにあります。例えば、フィットネスルームやリラクゼーションルームには十分な換気設備が必要なだけでなく、執務スペースとしっかりと区切られた個室空間でなければ、その効果が半減してしまう恐れがあります。
福利厚生の拡充を検討する際には、自社の職種や業務内容、従業員のニーズに応じた福利厚生制度やサービスを選ぶだけでなく、オフィス全体の空間設計の観点から、従業員にとって働きやすい環境づくりを目指すことが大切です。
福利厚生制度を成功させるための運用ポイント

福利厚生制度を導入しただけでは、その効果は最大限に発揮されません。従業員の間で制度やサービスが浸透し、彼らの満足度を高めていくためには、導入後の運用がポイントとなってきます。ここからは、福利厚生制度を成功させるためにおさえておきたい3つの運用ポイントについて解説していきます。
1.従業員への周知
せっかく魅力的な福利厚生制度を導入しても、従業員に知られていなければ意味がありません。新たな制度やサービスを開始した際には、その内容や利用方法を、わかりやすく周知することが重要です。例えば、社内報やメールでの発信、ポスターやチラシの掲示、イントラネット内掲示板でのお知らせなど、その方法は様々です。
社内周知において重要なポイントは、すべての従業員がいつでも福利厚生に関する情報に触れられることですので、情報のアップデートやメンテナンスが行いやすく、発信しやすい方法で続けることが大切です。
2.利用状況の分析
制度やサービスの利用状況の定期的な分析は、従業員にとって本当に喜ばれる福利厚生制度の実施に欠かせない取り組みです。導入後の利用者数や利用頻度をはじめとするデータ収集はもちろん、アンケートやインタビューを通して個々の満足度や意見・要望を把握することも、改善点の洗い出しに大きな効果をもたらします。
3.継続的な見直しと改善
従業員が「あったらいいな」「あったら嬉しい」と感じる福利厚生は、社会情勢や従業員の年代によって変化し続けるため、企業はニーズの変化に柔軟に対応した制度設計や見直しを行うことが大切です。
先述の従業員アンケートやインタビューは、従業員のニーズの把握にも役立つため、利用状況の分析結果をもとに、定期的な見直しや改善を行うようにしましょう。
福利厚生の導入事例
福利厚生が充実したオフィスにより、従業員の満足度や生産性向上に寄与している事例を紹介した記事もございますので、あわせてご参考ください。様々な取り組みの中から、自社に活かせるヒントを見つけてみましょう。

続きを読む
福利厚生とオフィスデザインの融合で企業成長を促進!

福利厚生は、従業員が心身ともに健康で、やりがいを感じながら快適に働ける職場環境づくりに欠かせない要素です。また、冒頭でも触れたように、昨今は企業が自社の魅力や独自性を発信するためのブランディングツールとしても、福利厚生は大きな役割を果たしています。
福利厚生を充実させることは、結果的に企業全体の成長につながるため、採用や人材育成、生産性や企業価値向上といった課題を抱えている場合は、福利厚生制度の見直しと拡充に取り組むことをおすすめします。その際、オフィスの空間全体で福利厚生との連携をデザインすることで効果の最大化を図ることができるため、オフィスリニューアルも視野に入れ、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。