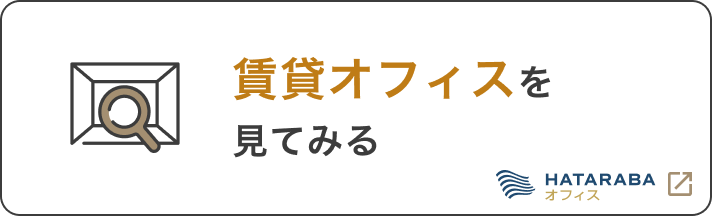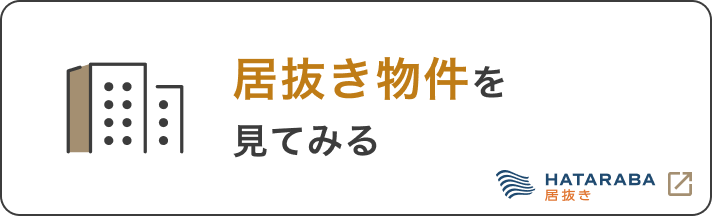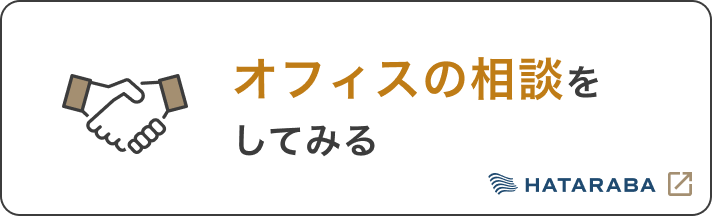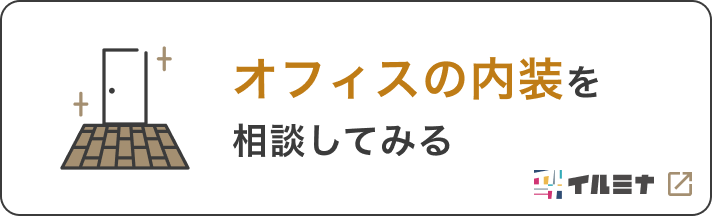-
- ファシリティナレッジ
-
貸主にメリットの多い定期借家契約とは?借りるときの注意点も紹介

希望のオフィス物件が見つかった場合、まずは契約内容をしっかり確認することが大切です。その中でも特に重要なのが、契約形態の違いを確認すること。
賃貸契約には定期借家契約と普通借家契約があります。これらの2つの契約形態には大きな違いがあります。オフィス物件を貸し出すオーナー側にとっても、利益や負担が変わってくるのでしっかり理解しておいた方が良いでしょう。
今回は、定期借家契約とはどのようなものなのかご紹介していきます。
目次
賃貸オフィス契約における定期借家契約とは?

オフィス賃貸物件を借りる際には、必ず賃貸契約を締結しなければなりません。賃料などの支払いばかりを気にして、契約形態を安易に読み流してしまうのはとても危険なことです。
どのような契約形態なのかによって、契約の更新や契約期間が違ってきます。
会社を守っていく意味でも、契約形態について正しく理解しておくことが必要です。
定期借家契約と普通借家契約の違い
契約形態には、定期借家契約と普通借家契約の2種類があります。もともと貸主が定めている契約形態なので、オフィス物件を契約する際に、借主が決めることはできませんが、どちらの物件を選ぶかによって負担が大きく異なります。
まず、両者の大きな違いは「契約の更新ができるかどうか」です。どちらも契約期間というものが定められており、契約期間を満了したら、更新または退去をしなければなりません。この場合、更新できる契約形態は「普通借家契約」で、必ず契約が終了してしまう契約形態が「定期借家契約」です。
また、中途解約についても大きな違いがあります。中途解約とは、何らかの理由で次の物件に移りたい場合に、契約期間の満了前でも途中で解約するということです。普通借家契約では、解約予告を期限内に行うことで中途解約が可能ですが、定期借家契約の場合は契約期間満了までに借りることが原則なので、中途解約はできません。
ただし、物件によっては特約があるケースもあるので、一概には言えません。
定期借家物件が少ないと言われている理由
貸主にとっては、中途解約される心配もなく、期間満了時に合わせて次の借主を見つければ継続的な利益になるため、「定期借家契約」物件は多いと思われるのではないでしょうか。
しかし、実際には定期借家による契約は普及していないのが現状です。国土交通省の調査では、定期借家契約の割合はわずか3%で、認知度についても、「知らない」が56.6%、「名前だけ知っている」が24.2%と、かなり低い数値の結果がでています。これに対して、普通借家契約の割合は96.4%とかなりの普及率であることがわかります。
借主にとっては契約期間が定められていると継続して借りづらいこと、貸主にとっては契約時の書面作成や期間満了時の通知などに手間がかかることが要因となり、定期借家契約が普及していないのではないかと言われています。
オフィスは定期借家契約?普通借家契約?

賃貸オフィスの契約には、普通借家契約物件の方がいいのでは?と思う方も多いでしょう。しかし、物件の使用目的によっては、普通借家契約物件よりも定期借家契約物件の方がメリットが大きい場合もあります。
自分の求める物件契約に合っているか、自分が貸し出す物件契約に不備はないかなどをしっかり確認するためにも、定期借家契約のメリット、デメリットを理解しておきましょう。
定期借家契約をするメリット
契約の更新や、中途解約ができないという特徴があるため、定期借家契約はオフィス物件を借りる側にとっては、デメリットが多いと言われています。このようなデメリットから定期借家契約を敬遠されてしまうと、入居者が少なくなってしまうため貸主側は困ります。
そのため、少しでも入居率を上げようと、定期借家契約の物件の賃料は周辺相場より安く設定される傾向にあります。賃料が安いということは、借主にとって最大のメリットと言えるでしょう。
また、借主が何か問題を起こしても契約期間が満了すれば退去を命じることができるので、普通借家契約よりも審査が通りやすいというメリットもあります。軌道に乗るまでの短期間だけ安い賃貸オフィスを利用したいと考えるベンチャー企業などにとっては、メリットが大きいでしょう。
貸主側にとっては、途中で退去される心配がないため、安定した収入を得ることが可能になるというメリットがあります。契約期間が決まっているので、契約期間満了後に次の入居者を探す準備もしやすいでしょう。
また、入居者に何か問題があった場合でも、立退料を支払わずに退去を命じることができるのもメリットの一つです。さらに、特約を事前に定めておくことで、賃料減額を防ぐことも可能です。
定期借家契約をするデメリット
定期借家契約を結ぶと、長期的に入居できないことが借主にとっての最大のデメリットと言えるでしょう。基本的には、更新ができない契約になっていますが、事前に定められている特約によっては再契約することも可能です。
しかし、再契約する場合には、普通借家契約の再契約に比べて倍のコストがかかります。継続的にオフィス物件を借りたい企業や、定期借家契約をしても、再契約する可能性が少しでもある場合には、注意が必要です。
また、中途契約がないということは、中途解約される心配がないため、貸主側にとっては安定した収入が得られるというメリットがあります。しかし、それは入居者が常にいる状態が保たれている場合です。人気がない定期借家契約物件では入居者が入りにくいため、家賃収入が得られません。定期借家契約は普通借家契約よりの敬遠されやすく、入居者が見つかりにくい点がデメリットと言えるでしょう。
そもそも、賃料が低いのに入居者が安定しないというのは貸主の経営を苦しめてしまうことにも繋がります。
また、契約は必ず書面でなければならず、契約満了時には通知を出さなければなりません。貸主にとっては、こういった手続きにおける手間も面倒に感じる場合が多いでしょう。
普通借家契約をするメリット
普通借家契約は契約期間が定められていないため、長期的に入居できることが借主にとって最大のメリットと言えるでしょう。また、中途解約も可能なので、万が一オフィスの移転が必要になった場合でも安心です。どのぐらいの期間借りたいのか決まっていない場合や、長期間オフィスを利用したい場合などは、普通借家契約の方がいいでしょう。
貸主側にとっては、契約が楽であること、更新料がもらえることなどがメリットです。契約に関しては文書でも口頭でもどちらでも良いので、手間がかからないという点では貸主にとっても借主にとってもメリットであると言えます。
また、賃料を低く設定しなくても普通借家契約では定期借家契約よりも入居者が決まりやすく、賃料を高めに設定することも可能です。不動産経営に余裕がない貸主などは、普通借家契約物件を貸し出して、安定した収入が得られる方が安心です。
普通借家契約をするデメリット
物件を借りる際に契約の更新や中途解約が可能で、長期間入居できる普通借家契約は、ほとんどデメリットはないと言っても過言ではないでしょう。あえてデメリットをあげるとすれば、「更新料の支払いが必要」ということです。万が一立退きを命じられるなどの最悪のケースになった場合でも、「立退料」がもらえるので、普通借家契約は借主に優しい契約であることがわかります。
反対に貸主側にとっては、「賃料減額を防ぐことができない」、「原状回復工事の手間と費用がかかる」などのデメリットがあげられます。また、自分の物件を返してもらうのに、立退料を支払わなければ退去させるのはほとんど不可能なので、無駄なコストが発生する場合もあります。
このことから、普通借家契約は借主に優しい契約であることがわかるでしょう。
定期借家契約する前に気を付けることとは?

契約満了時の手続きが必要であったり、普通借家契約よりも人気がなかったりする定期借家契約ですが、貸主にはメリットが多いといえます。上手に利用すれば借主にとってもお得な契約形態です。
しかし、定期借家契約は細かい規定があります。きちんと特徴を理解しておかなければ、損を被る可能性があるので注意しましょう。
定期借家契約の特徴を知っておこう
定期借家契約は、契約の更新がない期間限定の契約形態です。その特徴から、借主よりも貸主に多大なメリットがあると言えるでしょう。
賃料の安さや更新料の支払いがないことは借主にとっては魅力の一つです。一時的な利用のみで充分な企業などは、定期借家契約の方がいいという場合もあるでしょう。
定期借家契約をする際には、普通借家契約と様々な点が異なります。細かい点もしっかり確認しておきましょう。
契約方法と期間について
定期借家契約の契約は、必ず書面による契約が必要です。書面には契約期間だけでなく、特約などが記載されており、物件によっては「賃料は1ヶ月以内は減額不可」などの細かい規定が定められている可能性もあるので、事前にしっかり確認しましょう。
契約期間は1年~2年未満が最も一般的ですが、1年未満の短い期間に設定することも可能です。
中途解約について
定期借家契約は、原則中途解約ができません。しかし、事前に特約を締結しておけば契約期間内でも中途解約できる可能性があります。契約書の内容に中途解約に関する特約が記されていない場合、契約前に交渉が必要です。「契約期間の半分を経過していること」などの条件を提示すれば、特約を締結してくれる可能性も高くなるでしょう。
ただし、賃料が高額な場合が多く、急な家賃収入がなくなることによる貸主の負担が大きいため、ほとんどの場合は中途解約できないと思っていた方がいいでしょう。
更新はあるのか?忘れた場合は?
定期借家契約には更新はありません。しかし、どうしても退去したくない場合には、オーナーや不動産会社と話し合いをしてみましょう。仲介手数料や保証料、礼金などを支払う必要がありますが、双方の合意があれば再契約することも可能です。
ただし、通常よりもコストがかかることと、合意を得られなかった場合は必ず退去しなければならないことに注意しましょう。
定期借家契約では事前説明書の確認が大切
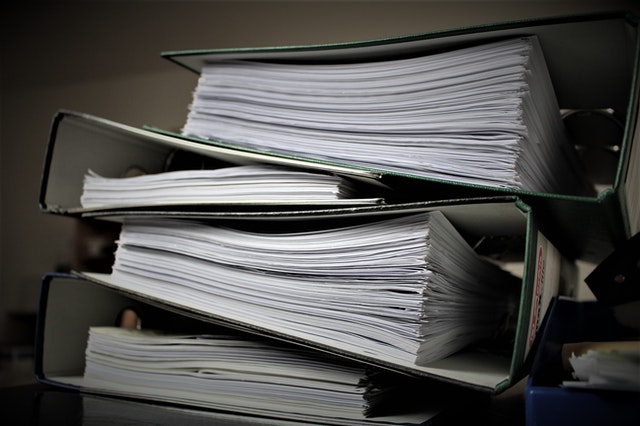
定期借家契約には細かい規定や確認事項が多いです。全て確認するのは面倒に感じるかもしれませんが、後からトラブルにならないためにも、しっかりと契約内容の確認をすることが必要です。
場合によっては再契約も可能ですが、その際にはいくつか条件があります。再契約するかどうかわからない場合でも、把握しておいた方がいいでしょう。
再契約したい場合には条件がある
定期借家契約を締結する際には、別個独立した「事前説明書」が必要です。賃貸オフィス物件の定期借家契約をして、再契約をする可能性がある場合、最初に取り決められている「事前説明書」の記載内容をしっかり把握しておかなければなりません。
なぜなら、再契約をするための条件が記載されている可能性が高いからです。
例えば、「賃料の滞納が〇回以下の場合、再契約について優先的に協議する」などの記載があった場合、賃料の滞納回数制限を超えてしまうと、再契約ができないことになります。再契約を検討しているのであれば、事前に確認し、条件を破らないようにしましょう。
再契約をする場合には、「契約締結→契約期間→契約終了→再契約を希望」といった流れになります。もっとも、再契約希望後は、貸主の合意を得られた場合は「再契約」、合意を得られなければ「退去」という決まりがありますので、条件を満たしていても必ず再契約できるというわけではありません。
定期借家契約物件を借りる時の注意点

再契約をする時以外にも、定期借家契約物件を借りる時には様々なことに注意しなければなりません。また、貸主側にとっても面倒な手続き関係を怠ってしまうと、問題が発生する場合があります。
ここでは、双方の立場からどのようなことに注意すべきかを見ていきましょう。
定期借家契約の終了通知がきたら
定期借家契約物件の借主は、定期借家契約の終了通知が来た場合、必ず期間満了までに退去しなければなりません。万が一、期間を過ぎてからも居座ってしまうと、損害賠償請求される可能性もあります。
しかし、契約期間内に終了通知が来なかった場合はどうなるのでしょうか。ここでは、オーナー側の視点から、定期借家契約の通知における様々なパターンに対する対処法をご紹介します。
延長期間が長期間にわたった場合
貸主であるオーナーが、万が一、定期借家契約の終了通知を忘れてしまったり、通知を出せなかったりした場合には、借主はどうすれば良いのでしょうか。契約期間終了後に、何らかの理由で終了通知を出せない場合は、「定期契約が終了していない状態」になります。
この期間は延長期間と言われており、あまりにも長期間に渡って続いてしまうと、新たな普通建物賃貸借契約が締結されたものと判断されてしまいます。具体的に、通知期間後何ヶ月までとは定められていませんが、定期借家契約が普通借家契約になりうる可能性もあるということを覚えておきましょう。
通期期間を過ぎたらどうなるか?
通常、1年以上の定期借家契約物件の場合、貸主は6ヵ月~1年前までに借主に期間満了及び契約終了の通知を出さなければなりません。
万が一、通知期間を過ぎてしまった場合には、できるだけ速やかに通知を出すようにしましょう。改めて通知してから6か月後が新たな契約終了日となります。ただし、定期借家契約物件の契約期間が1年未満の場合には、終了通知を出す必要がありません。
オーナーチェンジで購入した物件は要注意
物件の貸主になる人は、契約形態の確認に抜けが生じやすいため、特に注意が必要です。上記のような「終了通知を長期間出さなかった」などということはめったにないと思われるかもしれません。
しかし、オーナーが変わり、新しい物件オーナーが借主の契約形態を確認せずにいつの間にか通知期間が過ぎてしまっていた、というケースも少なくありません。
物件の貸主になる場合は、オーナーチェンジと同時に借主の契約形態や契約内容をしっかり確認しておきましょう。
まとめ

賃貸オフィスを借りる場合も、貸す場合も「契約形態」について理解しておくことが重要です。定期借家契約は貸主にとっても借主にとってもメリット・デメリットがありますが、貸主にとってのメリットが大きいといえるでしょう。
定期借家契約は、条件によっては有効に物件を借りることが可能ですが、契約締結前には事前説明書をしっかりと確認して、後でトラブルが起こらないように注意しましょう。
借主も貸主も定期借家契約を有効活用して、損をしないオフィス選びをしてください。