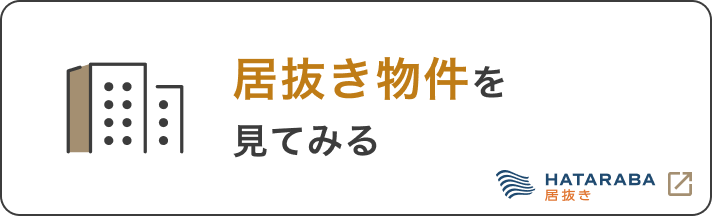-
- ファシリティナレッジ
-
建築基準法をオフィス担当者が理解すべき理由|外側と内側の論点

目次
建築基準法とは?

建築基準法は、建造物の敷地・設備・構造・用途について「最低基準」を定めた法律です。1950年に制定されて以降、改正を繰り返しながら現在まで運用され続けている法律です。
広く建造物は住居から職場、消費活動と生活の中に欠かせないものですが、建造物の存在が周辺に及ぼしかねない影響は重大です。
周辺環境に一切配慮せず高層の建造物が建つことにより、周辺の日当たりが悪くなったり、街の景観を損なってしまったりすることが考えられます。
閑静な住宅街に突如巨大な娯楽施設ができると周辺には騒音の被害が懸念される上、治安の悪化なども懸念されます。
また、安全性に一切配慮していない建造物は災害の際に倒壊してしまったり、構造上避難の妨げになったりと人命に関わらないとも限りません。
建築基準法は、こうした国民の生命・健康・財産の保護を目的とし、建築物に対して様々な観点から最低基準を設けています。
最低基準とは、自由な建築物を創造する権利との兼ね合いから法律に関する縛りは最低限度にとどめるべき、という考え方からあくまで目的のための最低限の基準値を定めていることを言います。
逆に言えば、建築基準法が定めている各種の基準値に満たないものについては、「違法」とされるラインであるとも言えます。
また、建造物に対してかかる制限は建築基準法のみならず、消防法、都市計画法、宅地造成等規制法など状況に応じて別の法規制を受けるケースもあります。
そういった場合については、建築基準法が定めているのはあくまで最低基準であり、別の法律により強い縛りを受ける場合はそちらの基準が適用されます。
今回の記事では建築基準法の中でも特にオフィス運用と関りの深い部分について、取り上げていきます。
オフィスの設計に影響を与える建ぺい率・容積率などの制限

建築基準法の中では建ぺい率・容積率や隣地斜線制限などの制限の範囲によって建築できる建物の規模に制限がかかります。具体的にどのような制限がどのような目的で設定されているのか、重要な部分を解説します。
建ぺい率
建ぺい率は土地全体の面積(建築面積)に対する建物の面積(敷地面積)の割合です。
建ぺい率=建築面積 / 敷地面積 ×100(%)
土地の持ち主が、建物をその土地いっぱいに建ててしまうと火災時に延焼しやすくなったり、避難経路が確保しにくくなります。また、土地いっぱいに建てられた建造物が並んでいると都市の景観を損なってしまったり、周辺の採光や風通しにも影響する可能性があります。
そういった悪影響が周りに出ないよう、土地の中に建てることができる建物の面積を制限するのが建ぺい率です。
容積率
容積率とは、土地全体の面積(敷地面積)に占める「建物の地上階の床面積の総和の割合」のことを指します。
容積率=建物の床の面積の総和 / 敷地面積 ×100(%)
建ぺい率は建物の敷地面積のみに対して適用されるため、建ぺい率しか制限がなければ理論上建てられる建物の高さには上限がなくなってしまいます。
しかし、どんな土地にも無制限なフロア数の土地の建設を認めていると、都市の景観を損なってしまったり周囲の日照権が侵害されてしまうリスクがあります。
建物の階数が多くなると容積率が上がっていくため、容積率に制限をかけることは必然的に建てられる階数にも制約がかかり、建物の高さが軽減されます。
また、特に集合住宅においては容積率が制限を受けることによって、必然的に一つの物件に入居できる人口の数に制約がでてくるため、区域の人口の急増を抑制するような効果も期待されています。
絶対高さ制限・隣地斜線制限
建物の高さに関する制限としてもう一つ、「絶対高さ制限」もしくは「隣地斜線制限」といった基準も存在します。絶対高さ制限とは、次の項目で説明する「用途地域」の一部で用いられる基準で、地域により10m、もしくは12m以上の建物を建築することができない制約です。
隣地斜線制限も容積率同様、高すぎる建物が建てられることによる周辺への悪影響を回避するために設定されています。
適用される条件は道路斜線、隣地斜線、北側斜線などが挙げられますが、具体的にどういった制限をどの程度受けるかは用途地域などの条件により異なります。
建築基準法の基準の数字は「用途地域」によって異なる
建ぺい率、容積率および絶対高さ制限もしくは隣地斜線制限の数字は全国一律で決まっているわけではなく、その区域が指定されている「用途地域」によって適用される数値が異なります。
例えば、一軒家や低層の集合住宅を中心としたいわゆる「閑静な住宅街」のエリア(例:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域)では景観を損なわないよう特に高さに関する制限は厳しく敷かれていますが、一方で娯楽施設やオフィスビルなどが立ち並ぶ繁華街のようなエリア(例:商業区域)などではむしろ高層のビルの建物の建設が用途に合うため、規制される数字の基準は低く設定されています。
入居している、もしくは入居を検討しているオフィスがどの用途地域に属するかによっては建築できるオフィスの規模に制限があるため、念頭に置いた方が良いかもしれません。
建築基準法に定められたオフィスの耐震性は時期により異なる

建築基準法の中で重要な事項の一つに「耐震性」が挙げられます。地震の多い日本では大きな地震が来ても倒壊しないような建物の建築を行うことは入居者や周辺環境を含めた人命を守ることに直結します。
建物の耐震性において重要な論点をまとめます。
旧耐震基準と新耐震基準
建築基準法の中には耐震基準が定められており、その基準を下回る耐震性しかもたない物件はそもそも建築することはできません。
この耐震基準は改正を繰り返すごとに強化されていますが、建築基準法の歴史の中でも最も大きな改定が行われたのが1981年の改正です。この改正の前の基準のことを「旧耐震基準」以降の基準のことを「新耐震基準」と呼びます。
基準としては、
旧耐震基準:震度5程度の地震で倒壊、破損したとしても補修すれば利用可能な水準
新耐震基準:震度6強、7程度の地震でも倒壊しない水準
といった差があります。
実際、1990年代以降起きた大きな地震において、その建築物がどちらの耐震基準に準拠して建築されたかは被害状況に大きな差をもたらしました。
物件に用いられている耐震基準がどちらであるかは、1981年の6月1日以前に建築確認を受けているか、それ以降に建築確認を受けているかによって異なります。
建築確認が完了した段階で建築確認済証が交付されるため、物件がどちらの耐震基準で建てられているか正確に把握することも不可能ではありません。
大まかな基準としては当時のオフィスビルが着工してから完成するまでには長くて2年程度の時間を要するため、1983年以降に完成した物件であれば新耐震基準が適用されている可能性が高いと考えることができます。
旧耐震基準でも安心できる物件の判断基準
新旧の耐震基準を見比べると、新耐震基準で建てられた物件を選択する方が安心なのは言うまでもありません。
一方で、旧耐震基準で建てられた建物の中にも十分な耐震性を元々有していたり、もしくは耐震補強工事を行うことで新耐震基準に適合した水準の耐震性を獲得している物件もあります。
築年数の古い建物は周辺の相場と比較して賃料が安く入居できる傾向にあるため、耐震面で安全な物件であればあえて古い物件を選ぶことにもメリットはあります。
ポイントとしては当該物件が耐震診断を受けているか、また診断の結果補強が必要であると判断された場合、必要な耐震補強工事を行っているかが挙げられます。そういったプロセスを経ている物件であれば、築年数が経過していても新耐震基準に適合する耐震性を持つことが保証されるため、一定の安心感を持つことが可能です。
旧耐震基準で建てられた物件では、入居前の重要事項説明において耐震診断の受診の有無や、受けている場合はその結果、および耐震補強工事の実施記録などの公開が義務づけられています。
ただし、耐震診断の実施は法的に義務付けられたものではありません。また、耐震補強工事には高額の費用がかかる可能性があることからそもそも診断を受けていない物件も多いため、この点については入居者側で知識を持ったうえで積極的に確認することが奨励されます。
建築基準法改正前に使用可能だったアスベストへの対応の判断基準

建築基準法に規定されている重要な事項の中で、耐震と同様に人命に関わる部分として挙げられるのがアスベスト対策です。
アスベストは安価で加工しやすく、かつ軽量な素材であり、かつては建築資材として非常に重宝されていました。
しかし、人体への有害性が明らかになり健康被害も如実になってくるにあたり、アスベストの使用は建築基準法の改正により大幅に制限されていき、現在ではアスベストを用いた物件の建築は実質不可能となっています。
そのため、築年数の古い物件においてはアスベストが使用されている可能性、ひいては社員の健康や人命に悪影響を及ぼすため、物件のアスベストの使用状況については慎重に確認すべき事項の一つです。
アスベストの警戒の必要の有無を判断できる建物の建築時期
アスベストの使用については徐々に制限が強くなっていったため、建物が建築された時期から、どの程度の使用規制がされていたのかの判断が可能です。
2006年以降であれば、アスベストの使用が実質的には全面禁止されているため、この時期以降に建築された物件であれば、アスベストの対策を考慮する必要はないといって差し支えありません。
また1990年代半ば以降であれば、1%以上のアスベストを含む拭きつけ工事が禁止と大幅にアスベストの使用が抑えられた段階であると同時に、アスベストの有害性が広く世間に認知されていることもあり、アスベストへの警戒の必要性は比較的低いと言えます。
最も警戒すべきは1970年代~1990年代半ばにかけて建てられた物件であり、この時期はアスベストの優位性が注目を浴びる一方で、危険性については強く認識されておらず、積極的に使用されていた可能性も高いため、注意が必要です。
アスベストの調査の有無は重要事項説明でなされる
アスベストの使用が懸念される物件の場合、アスベストの使用について調査や必要であれば対策を行うことが望ましいのは言うまでもありません。
この調査の有無や対策の有無は重要事項説明の中でなされることが義務付けられています。特に、アスベストの警戒が必要な時期に建築されている物件であれば、アスベスト調査の実施について入居者側で確認を行うことが大切です。
2021年の改正で物件の解体時にはアスベスト調査が義務付けられるようになりましたが、解体前の物件においては調査自体の実施は義務ではないため、一層注意深く確認を行うことが求められます。
建築基準法に適さない物件に入居するリスク(違法建築・既存不適格)

現在日本に存在する建物は全てが建築基準法に合致しているわけではありません。中には最初から基準を満たさずに建築されている、もしくは適切な工程を踏まずに違法状態の建築物となっている「違法建築」もありますが、法改正により厳格化した基準に沿っていない建築物もあります。
それらについて説明した上で、そうした物件に入居するリスクについて説明します。
違法建築とは?なぜ違法建築が成立する?
違法建築とはその名の通り、主に建築基準法をはじめとし、その他各種の法律に違反した状態で存在する建物のことです。
しかし、建築基準法の元では全ての建物は建築前に建築確認を受け、建築中には中間検査を、さらには完成後には完了検査を受ける必要があり、そのようなプロセスを踏む中で建築基準法に違反する建物を建造するほうがむしろ難しく感じられます。
実際、適切な中間検査や完了検査を受けておらず、建築確認を受けた設計図とは異なる物件を建築することにより違法建築が存在するケースもありますが、その後の物件の運用の中で違法建築の状態となるケースも存在します。
具体的には、
①完了検査を受けた時点では適法であったが、その後適切な申請を出さずに増改築を行った結果、違法状態となっている
②物件自体の建ぺい率・容積率などの規格は適法ではあるが、建築許可を受けた用途とは異なる用途で用いており、違法状態である(例:住居用という名目で建築許可を受けているが、店舗として利用している)
③完了検査を受けた時点では適法であったが、その後土地の一部を売却したことにより、建ぺい率、容積率の制限に抵触する状態となった
④登記を行っていない(不動産登記法違反)
といった事例が考えられます。違法建築はその違法となっている部分を改善するよう行政から是正勧告が行われるケースもあります。
既存不適格とは?
既存不適格とは、建築時は適法であったが、法改正により厳しくなった基準には適合していない物件のことを指します。
違法建築の中にも建築時点では適法なケースもありますが、既存不適格はその後積極的に改装、用途変更、土地の売買など違法状態となるような工程を踏んだわけではなく、あくまで法改正の結果、適法となる基準を下回った物件のことを指します。
国民の生命や住環境を守るために制定されている建築基準法が改定により基準が緩和されると言うことは基本的には想定されません。
一方で、建築された時点では法律を守っており、その後も違法な改装や用途変更をしていないにも関わらず、改正された法律に適合しないからといって違法建築と同等の扱いを行うのは不公平であり、日本の法律の基本的な考え方とも合致しません。
そのため、積極的に違法状態となっている違法建築と区別し、既存不適格という扱いを受けます。既存不適格の場合はすぐさま行政からの是正勧告の対象となるわけではありませんが、消防法に抵触するなど、周囲を含め安全性が懸念されるようなケースでは是正勧告を受けます。
違法建築や既存不適格の物件に入居するリスク
違法建築や既存不適格の物件であっても、所有し続けること、売買すること、賃貸契約をお行うことなどが直ちに違法になるわけではありません。
従って、仮に入居する建築物が違法建築、もしくは既存不適格であることを知って入居したとしてもそれ自体が違法になるわけではなく、何らかのペナルティもありません。
とはいえ、違法建築の物件で特に周囲への悪影響が大きいケースにおいては最悪のケースでは使用禁止や強制立ち退きといった措置を受ける可能性もあります。
また、違法建築、既存不適格の物件は現在の基準に不適格である部分を是正しない限りは新たな増改築は一切できないため、オフィスの改装工事などに制約がかかることもあります。
違法建築、既存不適格の物件は相場と比較し安い賃料で入居できるケースもありますが、基本的には避けるのが好ましい物件です。入居前の重要事項説明の中で、違法建築や既存不適格については明確に説明がなされるため、そういった物件ではないか事前に確認する機会は与えられます。
建築基準法によるオフィスづくりの注意点

ここまでの項目は主に建物のオーナーにとって問題となりうる点を中心に解説しました。入居の視点としては、オーナーや物件を判断する基準として上記のような考え方を持っておくことで安心感のあるオフィス入居が可能となる意味で重要ですが、建築基準法は物件のオーナーのみに関わる法律ではありません。
とりわけ、オフィスの賃貸契約においては借り手が内部のレイアウトを自由に施工して使用することが認められているケースも多く、オフィスの借り手側にも建築基準法の目的に合致した建物の利用を行うことが義務付けられています。
オフィスの利用者側が特に意識的に気をつけなければならない建築基準法のポイントについてまとめていきます。
廊下の幅に関する規定
オフィスの廊下の幅は、建築基準法により廊下の片側に部屋がある場合は1.2m以上、両側に部屋がある場合は1.6m以上の幅を設けることが建築基準法により規定されています。
この規定はオフィスの執務スペースの通路などに適用されるものではなくあくまで廊下に適用されるものであり、同じフロアを他のテナントと共有している場合は手の加えようのない部分なのであまり気にする必要はありません。
しかし、フロアごと占有的に賃貸契約をしており、フロアのレイアウトなどをつくり変えるような改装を試みる場合など建築基準法の制約を受ける可能性があるため留意が必要です。
消防隊侵入口の窓に関する規定
3階建て以上のオフィスにおいては、バルコニーなど特別な侵入経路がない限り火災時に消防隊が侵入するための窓が設けられています。
この窓には赤い逆三角形のマークが貼られており、この窓の前に荷物を山積みにしたり、パーテーションなどで区切って空間を遮断してしまったりといったオフィス運用を行うと、有事の際に迅速な消火活動ができなくなり、人命に関わるリスクがあります。
このマークの付けられた窓に関してはその目的を満たすようレイアウトや運用の中に制約が敷かれます。
排煙窓の設置
オフィスの上部には「排煙窓」と呼ばれる特別な窓が備え付けられているケースがあります。
この排煙窓は換気や採光の目的のためにあるものではなく、火災発生時に煙が室内に籠らないように逃がすことを目的に建築基準法により設置されています。
従って、その目的を阻害するようにパーテーションなどで他の空間と排煙窓を遮断してしまうような改装は認められません。
オフィスの防災への安全性を定める消防法も重要

建築基準法は基本的にはオーナー側に建物自体の構造や設備について規定を設けているものですが、入居者によるデザイン変更の裁量が広いオフィスの契約においては、場合によっては入居者側への規制となりうる部分もあります。
ただし、冒頭に述べた通り建築基準法はあくまでオフィス内部においては主に防災の目的で規定される「最低基準」です。
実際のオフィス運用においては建築基準法さえ守ればよいというものではなく、その他各種の法律に準拠する必要があります。
中でも特に防災の観点から強く指導を受ける可能性が高いのが「消防法」です。消防法が特にオフィスレイアウトに制約を受ける可能性が高い部分や入居者側にも関連性が高い部分について解説していきます。
オフィス設備内部へ設置が義務付けられているもの
消防法では有事の際に被害の拡大を防ぐためや迅速な避難を行うために建物内に設置が義務付けられているものが複数あります。
具体的には、消火器やスプリンクラーなどの「消火設備」火災報知器や火災通報装置といった「警報設備」非常用階段、避難はしご、避難用滑り台などの「避難設備」、そして排煙設備や連結送水管などの「消防活動用設備」が挙げられます。
これらの設置の義務は基本的にはオフィスのオーナー側にあるケースが多いですが、オフィスのレイアウトや運用によっては別途入居者側で設備を増やす必要性がでてくるものもあります。消防署の指導を受け適切な対応をとることが重要です。
パーテーションで空間を区切った場合の義務
「ハイパーテーション」という高さのあるパーテーションを活用することで、大規模な改装工事を行わなくとも簡単な施工だけで空間を仕切ることができ、執務フロアを分けたり、簡易な会議室を作成したりといったレイアウトの変更が可能です。
ただし、この際に気をつけなければならないのは空間をパーテーションなどで囲い完全に分断した場合、消防法上それぞれが独立した「部屋」とみなされます。
そして、その施工を行う際には消防署への届け出が義務付けられているとともに、消防署の指導のもと、それぞれの「部屋」において防災のためにスプリンクラーや火災報知器などの設備を設置することが義務付けられています。
避難経路の確保について消防署から指導が入るケースも
消防法には「店舗」に関しては廊下に関する明確な規定が定められていますが、オフィスにおいては具体的な数値が定められているわけではありません。
従って、「最低基準」の建築基準法に準拠した幅が確保されていれば法的には問題がありません。
しかし、実際には避難経路の導線がしっかりと確保されていなかったり、大きな荷物が置かれていたりと、避難に支障が出る可能性がある部分については消防署から改善の指導がある可能性があります。
また、執務フロアの通路については建築基準法、消防法いずれからも具体的な数値としての制約はありませんが、やはり状況によっては消防署からの改善指導の対象となるケースも考えられます。
避難経路の導線の確保は有事に社員の人命を守るために最重要事項の一つであるため、消防署からの指導などを受けるかどうかに関係なく、自主的に取り組むべき課題です。
荷物や備品を避難経路の導線上に通行の妨げになるよう置かないほか、配線がむき出しになっており足を引かっけてしまうようなリスクについてはOAフロア構造にすることによっても回避が可能です。
防火管理者や消防計画などの制定が求められる場合も
オフィスの規模によっては、防火管理者を選定し、消防計画の提出を求められるようなケースもあります。
防火管理者はオフィスの防災計画に関して責任を持つ法的に定められた立場であり、専門の講習を受けて資格を取得した上で、その責務に務める必要があります。
消防計画を作成した上で消防署に提出するとともに、定期的な防災設備の管理や社員向けの避難訓練の実施、火元責任者の選定、指導などの責務を負います。
また、多くのテナントが入居するオフィスビルにおいてはテナント入居者側から統括防火管理者を選定する必要があるケースもあり、場合によっては自社から選定する必要が出てくる可能性も念頭に置いておきましょう。
まとめ

建築基準法について、賃貸オフィスのテナント入居者が注目すべきポイントを中心にまとめました。
建築基準法について、入居者側でも一定の知識を持っていることで物件やオーナーの良し悪しを判断することにつながったり、オフィスのレイアウトを整えるにあたって違法状態にしてしまったり、災害時のリスクを高めてしまうことにも直結します。
建築基準法について正しい知識を持つとともに、その趣旨を理解して目的を実現できるよう、オフィス選びの基準を見直すとともにオフィスレイアウトの中でも防災にもいまいちど焦点を当て、安全性に配慮したオフィスづくりを心がけてみてください。