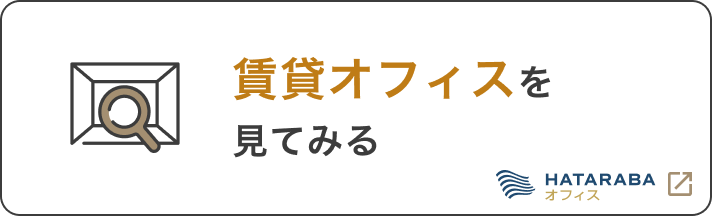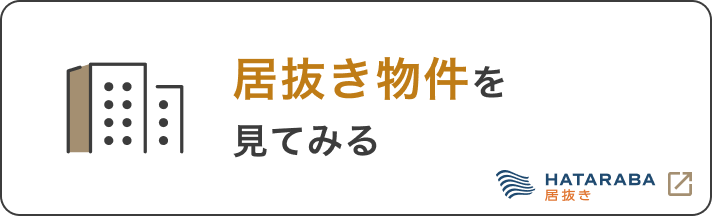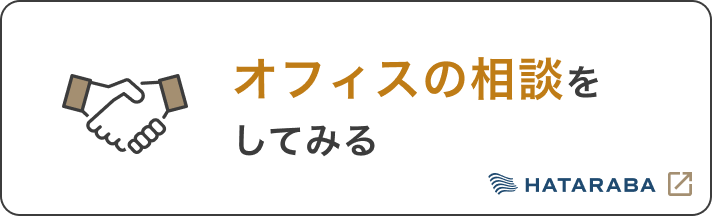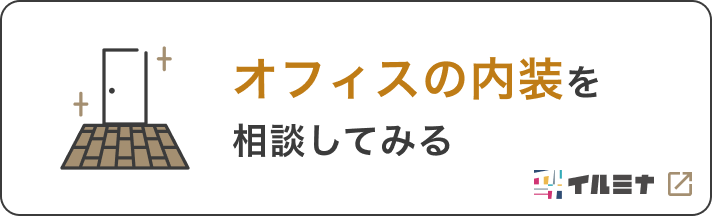-
- オフィスインタビュー
-
村田製作所 野洲事業所が進めるモノづくり革新。「ひらめき空間 EUREKA」が拓く共創の未来

セラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を手がける総合電子部品メーカー・村田製作所。その研究開発拠点であり、製造の拠点でもある野洲事業所では、活発なコミュニケーションや新しい発想が生まれる空間づくり・仕組みづくりに注力しています。今回は、同事業所の生産技術部門内に2022年オープンした「ひらめき空間 EUREKA(エウレカ)」を訪問し、空間のコンセプトや活用状況、イノベーションの創出につながった事例など、詳しくお話をうかがいました。

新卒で村田製作所に入社し、営業・営業企画を経て事業所の人事部門へ異動。人材育成など人事企画を担当する。その後、本社人事部へ異動し、全社人事制度の企画・運営を経験する。

新卒で村田製作所に入社し、商品開発や事業部の生産技術を経験した後、コーポレートの生産技術部門にて企画・管理業務全般に従事する。
目次
村田製作所の研究開発と製造の拠点「野洲事業所」
村田製作所野洲事業所の特徴とこれまでの歴史を、地域特性なども踏まえて教えてください。

野洲事業所は1987年に開設され、もうすぐ40年を迎える歴史ある事業所です。当社の研究開発と製造の両方を担い、製品だけでなく、生産技術・設備の開発・製造拠点でもあります。
開設当初は建物1棟で300人程度の規模だったのですが、徐々に拡張し、今では甲子園7〜8個分の敷地に20棟以上の建物が建ち、約5000人の従業員が働いています。敷地が非常に広いので、離れた建物へ行くときは自転車で移動することもあります。
地域とのつながりを大切にした活動も盛んだとうかがいました。
地域の小学校で出前授業を行っています。その授業を受けた小学生が大人になって当社に入社し、今では講師として出前授業を行っていたりもするんです。春には地域の人たちを招いて敷地内に咲く石楠花(シャクナゲ)の鑑賞会を開いたり、びわ湖マラソンの給水ボランティアをするなど、地域の方々との触れ合いを大切にし、「この町にムラタがあってよかった」と思われる事業所を目指しています。

そうした事業所の中でお二人は今、どういった業務を担当されているのでしょうか。
モノづくりの革新創出を推進するため、EUREKAをはじめとする共創活動や風土醸成などの企画・運営を担当しています。
野洲事業所の総務・福利厚生チームのリーダーとしてマネジメントと企画・運営を担当し、社員が安心・安全、快適に過ごせる環境やオフィスづくりを推進しています。
ありがとうございます。では、次に御社にとっての働き方と働く場所の役割について教えてください。
野洲事業所は、研究開発や製造など、さまざまな職種の従業員が働いていますから、まずは従業員一人ひとりが快適に過ごせる安心・安全な環境整備を第一に考えています。その上で、それぞれがリラックスし、アイデアや発想が生まれやすい環境づくりを大切にしています。研究開発職は実験が多いため現場での業務が基本となりますが、部署によってはリモートワークも活用し、それぞれに合った働き方を採用しています。
生産技術部門発 モノづくりのサードプレイス
今回ご訪問させていただいた「ひらめき空間 EUREKA」は、2022年にオープンされたと伺いました。そこに至る背景や経緯、目的をご説明いただけますでしょうか。

当社のコーポレートスローガン「Innovator in Electronics」には、エレクトロニクスの改革者として、エレクトロニクス産業のイノベーションを先導していく存在でありたいという思いが込められています。生産技術部門としてもモノづくりのイノベーション創出に取り組んできましたが、革新を生み出すためには環境や風土の醸成が不可欠であるという課題意識がありました。
そこで6年ほど前から新たな革新を生み出すための仕掛けづくりとして、さまざまな取り組みを行ってきました。その取り組みの一つが、「ひらめき空間 EUREKA」です。当時、生産技術部門内では技術展示や気軽にまじめなコミュニケーション(=ワイガヤ(※1))を行う場所がないという課題がありました。これを解決するために「思い切って作ろう」と企画し、実行に至りました。
会社としての取り組みではなく、生産技術部門内での取り組みということなんですね?
その通りです。
当社はトップダウンではなく、各部門で「こういうことをやってみたい」というアイデアがあれば、「ぜひ、挑戦してみてください」と主体的な行動にGOサインが出やすい企業文化があります。
もちろん経営層からは「本当に必要か」と確認はありましたが、新たなコミュニケーションスペースの必要性を経営層へ説明し、理解・了承を得たうえで、生産技術部門主導でこの取り組みを進めました。
具体的には、「ワイガヤ(※1)・偶発からひらめきを生むモノづくりのサードプレイス」というコンセプトをもとに、2020年頃から構想を練り、2022年に竣工しました。
こちらの名前「EUREKA」の由来を教えてください。
「EUREKA」とは、古代ギリシャ語で「分かった!」「 見つけた!」という意味です。アルキメデスが湯舟に入った際に、王冠が純金かどうかを調べる方法を閃き、思わず「EUREKA!EUREKA!」と叫んだといわれています。そんなひらめきの瞬間と喜びにあやかりたい――という思いから、この場所を「EUREKA」と名づけました。
「ひらめき空間 EUREKA」
実際にフロアを見学させていただきながら、3つの空間について、ご紹介していただきました。まずは、1つめの「出会い」のエリアから。
EUREKA1「出会い」のエリア

このエリアは来訪者が気軽に入れるよう、廊下に面した壁一面をガラス張りにしています。EUREKAは本質的にコミュニケーションと交流を目的とした空間であり、同時期に改装した隣の厚生棟に個人ブースを設けていることから、あえて当エリアには個人ブースを設置していません。

ここで展示会やイベントなども行われるのですか?

パートナー企業や社内の技術展示会など、月に一回程度は大規模なコラボレーションイベントを実施しています。生産技術系の展示会では装置を動作させるために、200V電源や真空・圧縮空気などの特殊なユーティリティが必要になる場合があります。もともと実験室として使用されていたスペースを改修したため、その時のユーティリティ装置をそのまま活用しています。生産技術部門の施設のため予算に限りがあったことから、コスト削減にもなりました。
EUREKAはスタッフルームと食堂のある厚生棟に挟まれているので、昼休みになると何百人もの従業員がこの前を通ります。そのため、ここで何かを展示していたら自然と目に入りますし、「何だろう?」と気になってふらっと入ってくる人も多いんですよ。
ガラス張りにこだわった甲斐がありました。

いろいろな形の椅子が並んでいますね。
はい。この一画を整備する際に“EUREKA的推し活”と称して、あらかじめ事務局でいくつかのテーマに沿った椅子の候補を挙げユーザー投票で決定したものが並んでいます。使用者が自ら選んだものなら愛着が湧き、より使っていただけるかな・・と。ユーザーと共に「シンカ」させていく取り組みのひとつの事例です。(※「シンカ」には、進化・深化・新化など、複数の意味を込めています。)

そして、その隣がEUREKA2となるわけですが、EUREKA1とはグリーンの壁で隔てられているんですね。

はい。植物など、自然の要素を取り入れることでストレスの軽減やリラックス効果が得られるというバイオフィリックデザインを採用しました。
雰囲気が良く明るい写真が撮れるため、社内報や社外からの取材など、各種撮影の背景として利用される機会が多くなっています。
EUREKA2 「対話」のエリア
EUREKA2は「対話」をテーマとしています。

スクリーンや講演台、スピーカーなど、本格的なAV設備を導入して、オンラインとリアルのハイブリッドコミュニケーションが可能な空間にしています。一般的なプレゼンテーションや講演はもちろん、ここをハブとして、複数の遠隔地を中継でつないだイベントも行っています。

上には電源が3本通っていて、頭上から電源が取れるリーラーコンセントを取り付けています。接続する機器のコードが地面を這わないので、見た目もスッキリしますし、人がつまずくリスクなども軽減できます。

後ろの小上がり部分以外はテーブルも椅子もモニターも自由に動かせるのですが、テーブルの形が台形で、使用者から「元の形に戻すのが難しい」という意見が上がったので、合わせる部分がわかるようにシールで目印をつけています。


後ろの小上がり部分はどのように活用されているんですか?

ここでミーティングを行うメンバーも多いんですよ。足を伸ばしてゆったりとくつろぎながら話ができるので人気で、よく利用されています。

EUREKA3「学び」のエリア
そして、その隣がEUREKA3「学び」の空間ですね。

ここは、イノベーションの土壌を養う空間で、先人の知恵や工夫が詰まった歴史ある装置を展示して技術の原点を学ぶ場として活用しています。一角には「まじめにおもちゃを作ってください」という課題の下で、新入社員が基礎知識や業務プロセスを学びながら製作した実習作品なども展示しています。


従業員の方々の反応はいかがでしょうか。この空間がイノベーションの創出につながった例があれば、合わせて教えてください。
EUREKAを利用した人たちに定期的にアンケートを取っていて、そこでは、アイデアの発想につながった、技術紹介や協働の話が進んでいる・・などの声をたくさんいただいています。本格的なイノベーションの創出にはまだ少し時間がかかるかもしれませんが、期待は持てると思っています。
ちなみに、EUREKAでの大規模コラボレーションイベント開催は、半年以上先まで予約が埋まっている状況。利用者が新たな利用者を紹介してくれることも多く、過去にはそうしたつながりから新たなイベントを行った事例もあります。出会いや繋がりがどんどん拡がり、新たな価値創造に繋がる・・といった好循環が回り始めています。
空間はイノベーションを創出するための手段

最後に、事業所で働く人へのメッセージや今後の展望などをお聞かせください。
これまでのように決まった時間にみんなで会議室に集まって「さぁ、新しいアイデアを考えましょう」と話し合うのではなく、ふらっと立ち寄ってたまたま顔を合わせた人と何気ない会話をする…といったゆるやかなつながりの中で、新しいひらめきやアイデア、イノベーションを生み出せるような空間になればいいなと思っています。野洲事業所には、本当にいろいろな専門家が集まっているんですよ。ですから、そうした人たちが自然につながれる空間づくりと仕掛けを、これからも追求していきたいと思っています。
EUREKAは社内でも良いモデルケースになっていて、他部門の人たちにとっても「こういうふうに変えていいんだ」という気づきにつながっているようです。もちろん、こうした空間はイノベーションを創出するための手段で、本当に大切なのはその空間をどう使って何を生み出すかということ。ですから、これからも利用者と共にこれまでに無いアイデアでこの空間を活用してイノベーション創出に貢献して行きたいと思います。そういうことも含めてここはどんどんシンカしていきますので、5〜6年後にはまた全然違う空間になっているかもしれません。
シンカし続ける共創の場、野洲事業所

開設から間もなく40年を迎える野洲事業所が、単に歴史を重ねるだけでなく、今なおイノベーションの「場」としてシンカし続けていることを実感しました。
本堂さんの言葉にあった、「ふらっと立ち寄り、何気ない会話をする」ゆるやかなつながりの中で、新しいひらめきを生み出す空間を目指すという姿勢は、多様な専門家が集う野洲事業所にとって理想的な共創の土壌だと感じました。
また、西山さんの「空間はイノベーションを創出するための手段であり、シンカさせていくもの」という言葉どおり、EUREKAは利用者の声を取り入れながら常に改善が図られています。すでに協働やアイデア創出につながる成果が出ていることは、この空間が未来のイノベーションを確実に耕している証です。
従業員の安全・快適さとともに、地域とのつながりも大切にし、「あってよかった」と思われる事業所を目指す野洲事業所。組織を超えた「共創」を促すEUREKAを中心に、そのさらなる発展を心より楽しみにしています。貴重なお話をありがとうございました。
取材先
株式会社村田製作所 野洲事業所
https://corporate.murata.com/ja-jp 公式サイト(注 ※1 ワイガヤとは、本田技研工業株式会社で取り入れられている議論手法です。職種や年齢、性別などの違いにかかわらず、多人数で気軽に議論をかわすことを指し、「ワイワイガヤガヤ」が語源となっています。)
(注 ※1 ワイガヤとは、本田技研工業株式会社で取り入れられている議論手法です。職種や年齢、性別などの違いにかかわらず、多人数で気軽に議論をかわすことを指し、「ワイワイガヤガヤ」が語源となっています。)